メディアのデジタル変革を進めるために、JIMAに期待すること——ダイヤモンド編集部 編集長 山口圭介さん
聞き手:JIMA理事/令和メディア研究所 主宰 下村健一さん
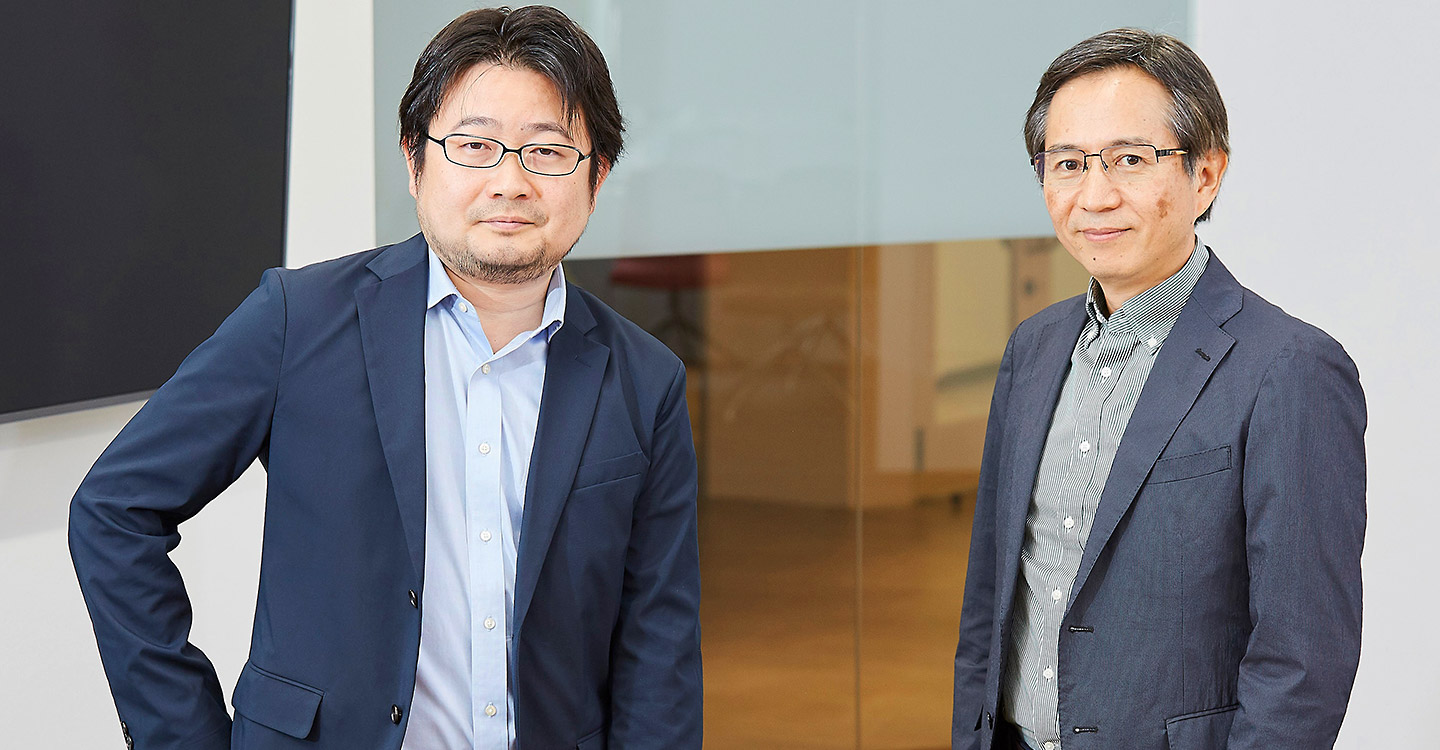
1913年(大正2年)にジャーナリストの石山賢吉が創刊した『経済雑誌ダイヤモンド』は、現在『週刊ダイヤモンド』となり、いまも幅広い業界のビジネスパーソンの必読誌となっています。そんな『週刊ダイヤモンド』とともに、急激に読者を伸ばしているのが、Web版の『ダイヤモンド・オンライン』。
実は運営元のダイヤモンド社は、2019年から、雑誌とWebメディア、両方の編集チームを統合し、「ダイヤモンド編集部」として新たな体制をスタートさせました。そのダイヤモンド編集部の編集長を務めているのが山口圭介さんです。
100年以上前に創業した老舗出版社が、編集部を統合し、デジタル変革を進める意義はどこにあるのでしょうか。そして、そんなダイヤモンド社がJIMA(インターネットメディア教会)に参加した理由は? JIMA理事で令和メディア研究所 下村健一の疑問に、山口さんが答えてくれました。
信頼実現の体制作り、持続可能性の追求を目指して
下村:ダイヤモンド社といえば、老舗の経済出版社ですよね。どういうきっかけでJIMAへ入会されたのでしょう?
山口:正直に言ってしまうと、私自身が直接関わったわけではなく、私の上司が、JIMAの事務局にお声がけいただいたのがきっかけです。でも、私自身もJIMAの話を聞いた時、入った方がいいと考えていました。

下村:それはなぜ?
山口:伝統メディアを含め、全般的にメディアに対する信頼度は落ちている状況です。業界として何かしらの対応が必要だと考えていました。メディアの信頼回復という意味において、JIMAという存在は大きな意義を持つと感じました。
下村:「大きな意義」とは、具体的にはどんな期待でしょう。
山口:「信頼できるメディアの運営」や「その実現のための具体的な体制作り」などの知見を共有する場として期待しています。メディアの持続可能性の追求もしていきたいですね。広告収入モデルやデジタル課金モデル、あるいは両方のハイブリッドなど、いろいろなやり方があるなかで、持続可能性の高いデジタルメディアの収益モデルが確立されると、メディア業界を取り巻く閉塞感の打開につながっていくのではないでしょうか。それを共有できる仕組み、協力体制が、JIMAを中心に出来上がってくると面白いと思います。
紙とオンライン版の編集部を統一! その狙いは?
下村:そうした知見の共有のなかで、ダイヤモンド社が担える役割はどのようなものでしょうか。
山口:私たちは2019年4月から『週刊ダイヤモンド』と『ダイヤモンド・オンライン』の両編集部を統合して「ダイヤモンド編集部」としてスタートを切りました。そして融合の象徴として6月には、デジタル有料課金モデルの『ダイヤモンド・プレミアム』をローンチしました。紙とデジタルの統合によってどのような化学変化が発生し、どんな可能性が見えてきたのか、徐々に知見が蓄積されてきているので、これについて共有ができると思います。
『ダイヤモンド・プレミアム』では、『週刊ダイヤモンド』や『ウォール・ストリート・ジャーナル』が読み放題なのはもちろん、ミリオンセラーの書籍なども続々公開される上、産業界に網を張る記者集団が手掛けたオリジナルの特集や連載が毎日配信されています。
一方で紙には紙の良さがありますし、それをデジタルにうまく転用する。また、デジタル発のオリジナル特集を紙の特集に再編集することによって、両媒体の質の向上にもつながっていく。われわれ自身もまだ完成形ができているわけではなく、模索中ですが、そういう点で協力できると考えています。
下村:それは興味深い。このインタビューに出てきたメディアも、紙とネットで運営が分かれているパターンがほとんどですが、そこに何か《統合しないことのデメリット》は見えてきましたか?
2つの編集部を融合して互いの連携が密になったことで、質もスピードも上がりました。また、データ分析担当記者、動画ディレクター、データサイエンティストなど、デジタル担当の増強効果は大きいと思います。
山口:多くのメディアがそうであるように、ダイヤモンド社としてもデジタルシフトを進めていました。そして私個人の問題意識でいえば、紙とデジタルの部員が一緒になって将来の絵姿を考えていかなければならないのに、編集部が別々であるが故にそれができず、結果として、それぞれが目先の数字を追って記事作りをすることに懸念を感じていたのです。
私は兼任役として、紙とオンラインの両方の編集部に関わっていたのですが、オンライン編集部はPVを取れる記事作りに注力しなければいけなかった一方で、週刊ダイヤモンド編集部はどうやってデジタル転換を図るべきかを考えるノウハウやリソースが不足していました。紙のパッケージングされた良さや伝え方を生かしてデジタル化を進めるにはどうすべきか、議論したくてもできる体制ではなかったんです。
「別々に存在していては、結局変わらない」と会社として決断し、統合することにしたわけです。
紙の雑誌とWebメディア、双方の最適化への方程式

下村:多くの人は、紙の記事のデジタル化といえば、文章や図版をそのままWebに転載すると思います。ですが山口さんは、「それだけでは成功しない」と。そこを詳しく教えてください。
山口:『週刊ダイヤモンド』の大きな特徴の1つとして「特集主義」が挙げられます。単発のニュースの集合体ではなく、テーマを絞った30ページから60ページの大特集を、起承転結のある物語としてパッケージングして付加価値を高めて展開しています。このパッケージングされたコンテンツをネットに落とし込むことは、意外と難しいんです。統合前のダイヤモンド・オンラインには特集記事はほとんどなく、単発記事として読まれることが大半でした。そのあたりをどう工夫するか、その正解はまだ見えていません。
下村:まだ試行錯誤中というわけですね。
山口:はい。デジタルでの大特集の予告編の作り方、パートの分け方ももちろんですが、雑誌で見開きの記事をスマホでどう見せるかなど、さまざまなハードルがあります。どのように編集部のリソースを配分して、紙とデジタル双方の最適化を図っていくか、早く方程式の解を見つけていきたいですね。
下村:そこで見つかる知見をJIMAで勉強したいという人はたくさんいると思います。
「読者を知る」ことがより求められる2020年、何ができるのか議論したい——MarkeZine編集長 安成蓉子さん
メディアのデジタル変革を進めるために、JIMAに期待すること——ダイヤモンド編集部 編集長 山口圭介さん
議論しながら走り、成果は上がっている
下村:紙とデジタルを一緒にして、異文化衝突みたいなことはありましたか。
山口:新生ダイヤモンド編集部では、PVはもちろん、6月から開始したオンライン版の有料会員数、それに雑誌の市販売上や定期購読者数と、4つの数字を追っています。そうなるとやはり衝突もありはしますが、皆改革の必要性は理解しているし、前向きに取り組んでくれています。4つの数字のバランスの取り方は難しいですが、みんなで議論しながら走っています。
下村:チャレンジだなあ。相当難産で、産みの苦しみになると思いますけど、いい効果が得られればいいですね。
山口:成果は上がっています。紙の市販部数は伸びていますし、2019年7月のオンラインのPVは過去最高を記録しました。有料課金会員も、想定より速いペースで積み上がっています。最初は全部の数字が下がると思っていたのですが、編集部を「記者チーム」、「デジタルチーム」「編集チーム」の3チームに分けて、それぞれが「やるべきこと」を明確にしていることで、いい流れになってきました。
下村:何が成功ポイントなのでしょうか。
山口:2つの編集部を融合して互いの連携が密になったことで、質もスピードも上がりました。また、データ分析担当記者、動画ディレクター、データサイエンティストなど、デジタル担当の増強効果は大きいと思います。
「鈍感力」と「嫌われる勇気」で、メディアのデジタル変革を実現する
下村:いま山口さんが進めている挑戦は、ほかの会社でもできるのでしょうか。
山口:やり切る覚悟を持てばできると思います。
下村:それはどういう覚悟ですか。
山口:メディア企業に限らず、「レガシー」を抱えた伝統企業が大きな組織変革をしようとすると、いろいろとハードルがあり、さまざまなハレーションが起きるものです。ダイヤモンド社には変化を恐れない風土があると思っていますが、やはり同じようなことは起きています。
それでも改革を進められるのは、編集サイドのみならず、経営者に覚悟があるからだと思います。当社では経営トップが「オールダイヤモンドで変えていこう」と示し、各局の幹部で意識を共有しました。
「実際に現場で指揮するのは大変でしょう」といわれることもありますが、もともと私は鈍感力だけは高く、だからこそこの立場に選ばれたのだと思っています(笑)。
心がけているのは、紙媒体の経験が長いからといって、紙の代弁者になってはいけない、ということ。また、紙とデジタルや、編集サイドとビジネスサイドなどの関係性において、偏りのない中立的な視点でやっていくという覚悟です。現場からのリアクションに関しては、できる限り迅速に丁寧に対応する一方で、さまざまな思惑が交錯しているので、ときに鈍感になる力も必要だなと思います。
下村:メディアのデジタル変革のためには、切り込んでいく必要もあるし、ハレーションに対して鈍感になることも必要だと。
山口:バランスを取るためには、鈍感力に加えて、嫌われる覚悟も必要かもしれません。もともと記者や副編集長時代、取材先が嫌がるようなことや不都合なことを取材することが少なくなかったので、適任といえば適任です。
例えば、2013年の創刊100周年記念号では「経済ニュースを疑え」という企画を組み、過去に『週刊ダイヤモンド』がいかに間違いを報じてきたか徹底検証しました。他社を批判するなら、自分たちのこともタブーなしで批判する覚悟が必要だと考えたからです。おかげで同業他社からも社内からも徹底的に嫌われました。
下村:「嫌われる勇気」(笑)。その意気で改革を進めているわけですね。
山口:自分たちだけに都合のいいことだけを書いていたら、そのメディアの信頼度やブランドはいずれ失墜してしまいます。
父の失踪——経済ニュースがいきなり家の中に
下村:もっと掘り下げたいのですが、それは次の機会に譲るとして。話は変わりますが、山口さんは、なぜ報道やメディアの世界に入ろうと思ったんですか。
山口:中学生のころは国際報道に携わりたいと考えていました。テレビの報道特番で、東西冷戦の崩壊やフィリピンのマルコス政権崩壊などを現場から伝える特派員を見たのがきっかけです。たしか「激動する世界地図」みたいなタイトルでした。こんな刺激的な仕事があるのかと、ミーハーな気持ちで国際報道に憧れました。
その気持ちに変化が起きたのは、高校時代です。バブル崩壊で父が事業に失敗し、失踪したことが転機になりました。それまで、経済ニュースはどこか遠いところにあるものだと思っていたのですが、それがいきなり家の中に入って来て——本当に、自分の足元にまでやって来たわけです。
その後大学に入った1997年に、山一証券の自主廃業や拓銀(北海道拓殖銀行)の破綻があり、アジア通貨危機が起こりました。こうしたニュースに触れる中で経済だけでなく、経済の「血液」である金融の仕組みにも興味が出てきたんです。徐々に国際報道から身近にある経済や金融ニュースに関心が移ってきたわけです。そして経済・産業分析をテーマにしているゼミに入り、経済部の記者を目指して、新聞社に入社しました。
下村:ダイヤモンド社に転職したきっかけは?
山口:新聞社では最初、社会部に配属されました。新人時代、警視庁の捜査一課担当などのベテラン記者に徹底的に取材手法を叩き込まれ、20代後半で東北総局に配属され、東北6総支局の事件キャップになりました。そこで数多くの殺人事件を取材するわけですが、その多くに貧困問題が絡んでいることを目の当たりにしました。
日本にはそれほど大きな格差はないと考えていましたが、それは誤りだと痛感しました。凶悪事件を起こすまでの過程には、驚くほど多くの貧困の悲劇がありました。そんな「起きてしまったこと」に反応するニュースだけではなく、いま起きている経済・社会現象を自分なりに理解したうえで、問題提起をするような報道がしたいと思い、経済出版社であるダイヤモンド社に入社しました。
下村:ご自身の体験を踏まえ、経済で人が不幸になるようなことをなくしたいと考えたわけですね。
経済は、知らないと怖い。だが怖さを煽るだけでもダメ
山口:経済って、とても怖いんです。知らないことの怖さが最も如実にあらわれる分野なので、正確なことを多くの人に知ってもらいたいと思っています。
もちろん、怖い怖いと煽るだけではダメで、「リスクをきちんと知ったうえで、自分で判断し、動きましょう」と伝えたい。保険ひとつ取っても、不動産を購入するにも、子供の教育にも、私達の身の回りのライフイベントは経済やマネーと密接に関係しています。そういうことを考えるきっかけを提供できたらいいな、というのが願いです。
下村:このインタビューでは、登場していただいたみなさんに読者の方へのメッセージをお願いしています。その言葉で締めましょう。
山口:いまの話に補足する形になりますが、以前のJIMAのインタビューでJX通信社の米重さんが「ファクトとオピニオンを切り離して考えよう」と話されていましたよね(「テクノロジーの力でジャーナリズムをビジネスとして成立させたい」)。
私もそれには賛成で、客観的な事実がどこにあるのかしっかり見る必要があると思うんです。
隣国との外交問題もそうですが、感情ではなく、データと客観的な事実に基づいて思考することが重要で、一方的なものの見方を疑う視点の記事が書ければ、読者の行動も変わってくるはずです。そんな姿勢で皆さんに経済ニュースを届けていきたいと思っています。
(まとめ:岩崎史絵/写真:ATZSHI HIRATZKA)

